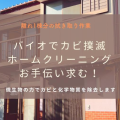先週土日で35組のマイ田んぼ2025メンバー半々ずつ脱穀の予定が
土曜に天候で中止。
急遽予定空き、
午前にマイ田んぼメンバーにオダ掛け天日干しの意義理由を
文にしてメールで送り(後述)、
昼から旭市の妻のリノベに赴く。
風通しが悪くカビ生えやすい箇所、解決模索して壁ぶち抜くことに。
気も氣も流れるようになる。
夜、藁でカツオを炙ってカツオのたたき、うまい!
翌日曜、35組と収量少ない人のために補填するコモンズ田の脱穀。
脱穀に使うコンバインのご機嫌よく故障なしで夕方までに全員分終えた。
夕刻の田んぼでアジア太平洋資料センターのドキュメンタリー映画
『お米が食べられなくなる日』続編制作でインタヴューを受ける。
ここまでそれぞれ田植え・草取り・稲刈りと35組のソロプレーだが、
この日だけは完全協働作業、
嵐のような忙しさだが互いが自発的に協力し合う姿が自然と生まれる環境を醸した甲斐あり、
疲れ果てても充実した顔が溢れる。俺も疲れた〜!


翌日の昨日午前、妻の愛犬アッシュが18歳で天国へ赴く。
お見事な逝き方だった、最期は俺の手のひらの中で、ありがとうね、安らかに。
疲れ癒して午後、髙坂自身の脱穀、夜は十五夜お月さん。そしてまだの稲刈りへ。
あとこれだけ、終わるのが寂しい。

オダ掛け天日干しの意義理由をここに転載。
〜〜〜
なぜ、オダ掛け(ハサ掛け、など地方によって違う)するのか。
そしてなぜ日本中の普通の米作りではオダ掛けをしないのか。
刈る寸前まで稲は土から栄養分を汲み上げています。
刈った折も茎には上昇移動中の栄養分があるのです。
オダに逆さに干しておくことで茎を移動中だった栄養分、
要は糖分や油分が概ね1週間で籾に移動してお米が美味しくなるわけです。
オダ掛けをするとお米の重みが5%増えると言われます。
その5%とはまさに茎から届いた栄養分なわけです。
米1俵60キロ、オダ掛けすれば63キロになるということです。
だから滅多に手に入らないオダ掛けのお米は美味しい、
と言われる所以です。
日本の米はブランド化されてきましたが、
とはいえ、
普通の米とブランド米と美味しさに5%の差があるでしょうか!?
仮にあったとしても僅かでしかもそこまで舌で判断できるでしょうか!?
ということはオダ掛けしたお米は、
日本一美味しいお米、と言っても大袈裟でないし、
概ね間違いないのです。
もう少し長い時間オダで干しても構いません。
穂の中身が熟してくるし、
太陽や風に晒されることも旨みを増すことに寄与するでしょう。
そして乾かすほど籾の水分も減って1年間保管する条件が整っていきます。
水分計という計器で15.0以下にすると
来年の梅雨や夏も越えられるお米の条件になります。
もっと長期間で乾かせば
虫が湧くことやカビることのリスクを減らせますが、
美味しさが落ちますね。
加えてオダ掛けしておく時間が長いということは、
台風や大雨でオダごと倒れて稲が濡れてダメにしてしまうこともあります。
倒れて水についても2日以内に救出して乾かせば大丈夫ですが、
それ以上時間経つと水を吸って芽が出てしまいます。
また泥だらけの田んぼで、しかも雨後の水浸しの中で、
組まれたまま倒れたオダを立て直すことの大変さ、
掛かっていた稲もオダに絡み、稲束自身も水を吸って重く、
ほうぼうに散って泥に塗れてますから、
そりゃ、救出は大変なんです。
(幾度となくその苦労をしてきています)
だから倒伏のリスクを減らすなら1週間から10日でオダから降ろし、
脱穀して籾にして、
その籾を晴れた日にブルーシート(昔はムシロ)に広げて
水分計で15.0以下に下がるまで乾かします。
(その作業を明日の脱穀後にしたいのですが、
午後晴れるものの時間があるか)
かつてはどこの地方でもしていたこの、
労力掛かるとはいえ米が美味しくなる合理的な作業、
なぜしなくなったのか。
労力省き(人力)合理性、時間合理性、リスク回避合理性、
つまりは経済合理性です。
みなさんも経験したように、
50㎡だけでもそれなりに大変な作業です。
皆さんはオダの代わりに簡易に設置できるホスベーを立てましたが、
本来は山から竹や細木を切り出し、
田んぼに運び、3本を縄で結んで組んで、、、、
大変な作業です。
(田んぼ継続してるみんなはやってますが、、、笑)
大きな農家さんだとしたら
毎年竹や細木を切るのも大変だし、
保管する場所もかなり必要になります。
竹も木も土に触れていると痛むし、雨に濡れても痛みます。
なので高床にして屋根も必要ですから。
相当の量です。
農家さんの数は国民の1%を既に切りました。
今年、おそらく110万人を下回ります。
1人の農家さんが百人分以上、
及び産業用(飲食店など)の米を作っているという単純計算になりますね。
当然、広大な田んぼ面積になります。
参考までにみなさんの収穫量は少ない人で5〜10キロ、
多い人で15〜20キロです。
お米の1人消費量は国の調査で50キロくらいです。
少食の女性で30キロくらいと思います。
そう考えると国民全員を賄える見渡す限りの広大な農地面積を、
もしくは山がちのエリアではいくつもの離れた田んぼを巡り巡り、
手作業で出来ませんね、手植えも、草取りも、稲刈りも、、、。
草取りの大変さんは身に染みたことでしょう。
広大な田んぼでは到底出来ませんから、
機械を使うとか、危険な除草剤を使わざるを得ない。
だから単なる消費者目線で農薬や除草剤を使う農家はダメだ、
なんて言えないのは、
草取りをした皆様ならお分かりになると思います。
安全安心で農薬・化学肥料・除草剤を使わないお米を
国民の多くが望むなら、
その国民に多くが
直接間接自ら少々なりとも自給する必要があるということですし、
それが私が長年訴えていることです。
さて話戻して、
広大な面積で大量に機械で刈った稲を広大で点々とした田んぼごとに
オダを立てて干すなんて不可能でしょう。
なので500万から1000万円のコンバインで稲刈りし、
そのまま乾燥機というでっかい500万から1000万円級の機械に
運んで入れて
電気を使って数時間で水分計15.0%以下にします。
当然、茎に移動中の栄養分は入りません。
そもそもコンバインは
稲を刈って機械の中で脱穀して籾になって出てきますから。
大規模な米農家さんほど借金が膨大になります。
大変です。
一年に一回しか使わないのに機械のメンテナス料も掛かります。
当然に大量の作業ですからたいてい1シーズンに1回は壊れます。
その修理代も掛かります。
それなら機械を地域でシェアして使えばいいのでは?
それはいい案のはずなのですが、、、、
機械というのは使う人によって癖が出ます。
だからいろんな人が使うとますます壊れやすくなります。
ソープロでも草刈機をかつていくつも管理していました。
ですが1年以内でたいてい壊れます。
たくさんの人が使うからです。
1人で使えば普通に5年くらい使えて当然なのですが。
同じように、
私たちSOSA PROJECTも
コンバインや脱穀機械を買えばいいじゃないか、
という声もあるんです。
でも今使っているコンバインなどもいろんな人が使うので、
どんどん壊れます。
高いお金出して新しい機械を導入してもすぐ壊れて、
メンテナンス代も掛かることは経験値としてわかっています。
なので古い中古のコンバイン
(脱穀機能だけ使い、刈り取り機能は使いません)を、
壊れては直し、壊れては直し、
と1シーズンに5〜10回、壊れては直し、
と使っているのです。
今シーズンも既に継続メンバーが各々脱穀する中で3回は壊れて、
都度私たちに連絡が来て田んぼに出動し、
私たちで治せなければ
機械に強くて親しい有機農家さんに来てもらって治しています。
時間ができたので長々と書きました。
先日の稲刈りからのオダ掛け、
明日の脱穀、
そして明日できるかわからず来週作業になるかもしれない籾の天日干し、
ご理解いただけたかと思います。
髙坂